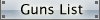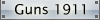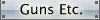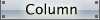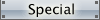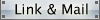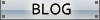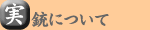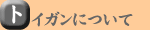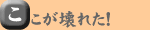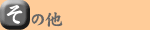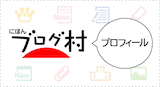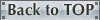WA/コルトM1911 U.S.ARMY

| ジャンル | 作品 | 使った人 |
|---|---|---|
| ――― | ――― | 米軍 |
| ※TV・映画では俳優名、漫画・アニメ等では役名を記述 | ||
その名の通り米軍が1911年に採用した初のオートマチック拳銃です。
ただ改良型のM1911A1の方がずっと長く採用されてた為
こちらが「ガバメント」の代名詞になった感があり、元祖でありながら影に隠れた印象があります。
米軍がオートマチック、しかも45口径を採用した理由として有名なのがフィリピンの先住民族モロ族との戦闘です。
スペインとの米西戦争に勝利してフィリピンを獲得したアメリカですが、その治安に手を焼いていました。
モロ族と戦闘になったのもそんな時期です。
当時米軍は38口径のリボルバーを採用。
他方モロ族の武器は弓と槍。この戦闘は楽勝だと思われました。
ところがモロ族の戦士たちは1、2発の銃弾を受けても全く怯まず、
中には全弾6発打ち込んでも前進を続け、その米兵を刺し殺してしまう事件まで発生。
米軍は大変な衝撃を受け、38口径への不信が決定的になります。
尚、モロ族には勇敢だった事以外にも、麻薬に似た薬物を習慣として常用していたとの話もあります。
ともかくも「一発で倒せる強力な拳銃」を求めて次期採用拳銃のトライアルが始まります。
ついでに速射性と再装填の利便性から種類はオートマチックとされました。
ここで出てくるのがジョン・ブローニングとコルト社です。彼らはコルトM1900をトライアルに提出、
その後の要求に応じて
M1900→M1902→M1905→M1909→M1911
と改良を続けます。
最終選考でコルトM1911は対抗馬のサベージM1910と一騎打ちとなり、トライアル中全く故障しなかったM1911が採用されます。
その後第一次世界大戦を経て米軍はM1911の改良を要求。1926年にM1911A1として採用され、M1911は消えていく訳です。
採用年数を見てみると、
・M1911
1911年〜1926年(15年)
・M1911A1
1926年〜1985年(59年)
ですから、後者で年数も長いA1が有名になるのも無理はありませんね。
中古をネットオークションにて購入。開けると「限定品」の紙が入っていてびっくり。
予備のパーツを買いに行こうと思っていたのですが、難しそうです。
外観上の特徴(A1との違い)は以下の通りです。

スライドのリーフ・カットのアールがきついです。またリーフ先端の▼カットもA1より深いです。 フロントサイトとリアサイトは現代では無いも同然の見づらさです。

ロング・トリガーでフレームに指掛け用のカットがありません。
最近のタクティカル45オートはロング・トリガーが主流なので先祖がえりした訳です。 推測ですがA1で短くなったのは「引き易くて暴発させない為」の初心者対策じゃないでしょうか。 グロックが暴発対策でトリガーを重くしたのと同じ理屈です。
他方フレームのカットはあった方がいいです。A1よりグリップが太く感じてしまいます。

ハンマー・スパーが長く、他方グリップ・セフティのテールが短いです。
SCWではハンマーダウンの位置に拘っており、手動デコッキングでファイアリングプレートにピタリと付きます。 この状態でトリガーを引いてもピクリとも動きません。
他方Rタイプに比べてハンマーがフニャフニャ(スプリング?)だと思いました。

ピンボケで見づらいですが、つるつるのストレート・ハウジング。
これも現代では先祖がえりしています。ただしチェッカリング必須です。
ガバメントは日本人でも握りやすい、細いグリップをしています。 手の大きなアメリカ人では発射時に手の中で踊ってしまうこともあるでしょう。
A1でハウジングにアールを付けたのはこの為ではないでしょうか。
ピン類を除き、主要金属パーツは塗装です。汗や錆には強そうですが、ちょっとガッカリ。
古い銃なんでブルーイングして欲しい所です、限定品ですし。
いよいよ実射ですが、Rタイプに比べリコイルが弱くなっている気がしました。
「Rタイプはファイアリングピンが直線なのでパワーがある」
ショップで聞いた話ですが、そう感じました。
それでも他社製品よりずっとリコイル強いのは間違いありません。
本家コルトの、元祖45オート。過去バージョンの限定品で終わるには惜しいです。SCW3で過去のモデルが続々リメイクされていますので、是非M1911もSCW3化をお願いしたいです。
| 部品 | 症状 | 対策 |
|---|---|---|
| 本体 | 装填不良 マガジンをBB弾に目一杯詰めてスライドを引くと、1,2発飛び出してしまう症状が時々ある。 |
とりあえず様子見 |
雰囲気を考えると、是非とも木製グリップに付け替えたいです。